 5月開幕の女性ドライバーによるカーレース「KYOJO(キョウジョ)カップ2025」に、静岡県で今年新たに発足したチーム「富士山静岡レーシング」が参戦する。ハンドルを握るのは、3児の母でレーサーの夫を持つ御殿場市の細川由衣花さん(32)。富士スピードウェイ(小山町)を舞台に繰り広げられる迫力のレースを地元企業、学生が後押しする地域密着の挑戦が走り出す。
5月開幕の女性ドライバーによるカーレース「KYOJO(キョウジョ)カップ2025」に、静岡県で今年新たに発足したチーム「富士山静岡レーシング」が参戦する。ハンドルを握るのは、3児の母でレーサーの夫を持つ御殿場市の細川由衣花さん(32)。富士スピードウェイ(小山町)を舞台に繰り広げられる迫力のレースを地元企業、学生が後押しする地域密着の挑戦が走り出す。■最高時速約220キロ、10~20代と肩並べ
雨が降りしきる3日の富士スピードウェイ。参加チームによる合同テストで、最高時速約220キロのフォーミュラカーが水しぶきを上げて疾走していた。タイヤから白い湯気を上げてマシンがピットに到着すると、メカニックのスタッフがすぐに状態をチェック。運転席から降り立った細川さんは取材に「10~20代の若いドライバーが多いが、年長者でも体力で負けたくない。静岡県のチームとして愛される走りをしたい」と意気込みを語った。
9年目となるKYOJOカップは、11月までの全10戦で獲得した総得点数を競う。今年から参加ドライバーを20人に限定し、フォーミュラカーを導入。主催者が管理するマシンを各チームが借り受けてレースに臨むため、資金力よりもドライバーの技術と体力、チームの結束が勝敗を分ける。富士山静岡レーシングの窪田善文監督(36)は「まさにアスリートによるスポーツ。迫力のレースが感動を与える」と魅力を説く。
■静岡工科自動車大学校学生も協力
同チームのスタッフ陣には、静岡工科自動車大学校(静岡市葵区)2年の渡辺雅矢さん(19)もメカニックとして名を連ねる。子どもの頃からのレース好き。教諭の誘いを受けてチームに加わり、「現場のプレッシャーは授業で味わえない。行動に緊張と責任が伴う」と表情を引き締める。
チームコンセプトは女性活躍やインバウンド(訪日客)促進に加え、若者の車離れが進む自動車産業の持続的発展を掲げる。「世代や性別、国籍を超えて魅力を感じられるチームを目指す。まずは多くの方に知ってもらいたい」と、運営するCSAレーシング(同市)の小島孝仁社長。富士スピードウェイが本県にある地元の優位性も生かし、さまざまな仕掛けで地域活性化を狙う。
<KYOJOカップ> 「競争女子」に由来し、女性のレーシングドライバーが互いに公平な環境で競い合う。2017年に始まった。25年から導入されるフォーミュラカーは運転席やタイヤがむき出しで車体が軽く、空気抵抗が少ないため、コーナリングも含めて走行スピードが速い。5~11月に富士スピードウェイで全5大会が開催され、それぞれ土日で1レースずつ、計10レースを行う。全長約4・5キロのコースで、土曜は10周、日曜は12周の順位を競う。

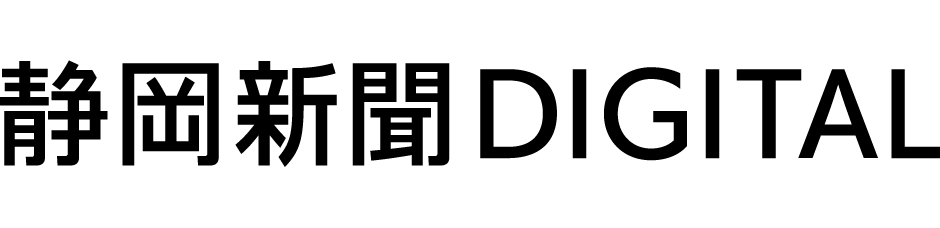

 シェア
シェア ポスト
ポスト LINEで送る
LINEで送る






























































