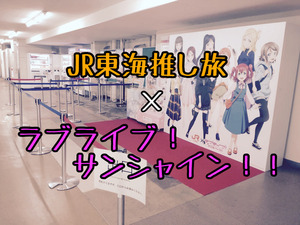沼津市を舞台にした「ラブライブ!サンシャイン!!」をきっかけに同市へ移住した6人が、自分と沼津との出会いや移住後の生活を語る。たったそれだけといえばそれだけなのだが、人生の価値についてさまざまな示唆がある、有意義な時間だった。
私は沼津市の東部総局に勤務していた時期、2016~2018年あたりの同作品と沼津市の関わりについて自分の書いた記事を参照しながら約30分講話した。来場者70人のほとんどが「ラブライブ!とはなんぞや」について、知識を共有している安心感があったため、とても話しやすかった。

登壇した6人と自分が同じ地平にいることがはっきり分かった。私はメディアの人間だが、2015年3月に初めて沼津に住んだ「エイリアン」である。海山が近く、市の中心地を優雅に1級河川が流れ、個人経営の魅力的な飲食店があちこちにある。すぐにこのまちが好きになった。
ただ、まちの人たちはどこか自信なさげだった。人口は右肩下がり、西武百貨店は撤退、JR沼津駅の高架化事業の行方は不透明…。「昔は良かったんだけどね」という商店主を、「そんなことないですよ」と励ましながら、記者という立場からの逸脱も少し感じていた。
2016年になり、「ラブライブ!サンシャイン!!」のプロジェクトが始まると、多くの「聖地巡礼」の人々がやってきた。彼らもまた「エイリアン」である。そして、多くの巡礼者は私と同じ行動を取った。まちの人たちを励ましたのだ。「沼津、いいところですね」と。
私の声は小さかった。でも、彼らの声は大きかった。一人の声ではない。数が桁違いだ。「沼津、いいところ」の声は、確実にまちの人の意識を変えた。「みんな、沼津を褒めてくれる」とうれしそうに言う沼津市民を何人見たことか。まち全体のシビックプライドの向上を肌で実感した4年間の沼津暮らしだった。

「沼津スライドトークイベント」で登壇した方々の、移住のきっかけはさまざまだった。ただ、「ラブライブ!サンシャイン!!」のファンとして訪れた沼津に、「住みたい」と思うほどの価値を見いだした点は一致する。そしてそれは私も同じだ。
登壇者からは「沼津のヒーローになりたい」という声も聞かれた。すでに彼らにとっての「地元」は沼津なのだ。
講話の中で、当時静岡英和学院大人間社会学部の毛利康秀准教授が行ったフィールドワークについて紹介した。2018年3月2日付の記事になっている。「沼津の街に愛着を持っているか」という問いに対し、作品のファンは54.5%が「とてもそう思う」と答えた。一方で沼津市の商店主は36.5%、高校生は13.4%である。
この時「とてもそう思う」と答えた54.5%の一部は、実際に沼津への移住を決断したのではないか。イベント終盤に移住者の皆さんと懇談しながら、そんなことを考えていた。
沼津への愛着が強い人々が集いつつある。「エイリアン」だった彼らが、まちづくりに本格的に関わるようになった時、街路の風景も変わっていくのだろう。




 シェア
シェア ポスト
ポスト LINEで送る
LINEで送る