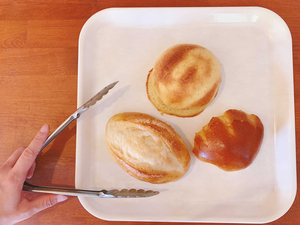味噌仕込みワークショップは春と秋の年2回開催
「発酵食品の試食をしたり解説を聞いたりできるのも、皆さん楽しみにしているようです。味噌は熟成するまでに時間を要しますが、手づくりならその変化を目の当たりにすることができます。このくらいの熟成だったらこんな風に使えるとか、前の年の味噌とブレンドしてみようとか、味の変化と使い方を楽しめるのが一番の醍醐味ですね」。大中寺副住職の下山光順さんが話してくれた。

下山光順さんと特産の大中寺いも
愛され、親しまれ、受け継がれ……今に生きる「麹の世界」
清水町新宿区。車が往来する店舗・住宅街に、まるで居場所を間違えたかのような、瓦を敷き詰めた大きな屋根とガラス戸が印象的な古い家屋がある。ここが中村屋麹店だ。現役なのか製造所跡なのか……その外観からは判断がつかず、ドキドキしながら少し重い引き戸を開けると、麹を納めた年季入りの大きな幾重もの棚が目に飛び込んでくる。お客さんの注文に応じて都度麹を量り売りする、昔ながらの販売スタイルだ。見渡す限りの調度品はどこか懐かしく居心地が良い。店を切り盛りする中村屋5代目店主中村一紀さん、真咲さんご夫婦の年代を想像すると、新たに買い足した家具や道具があるだろうに、「建物に馴染むように、あえて中古を買い求めた」のだそう。聞けばこのご夫婦、そして先代であるご両親も、麹屋を継ぐ前はクリエイティブ系の仕事をされていたという。研ぎ澄まされた感性と代々受け継がれたこだわりが、建屋内の至るところで息づいている。

ここだけ異空間のような中村屋麹店の入り口
当時は自宅で獲れた米や大豆で親戚縁者の一年分の味噌を仕込む農家が多かった。高度経済成長期に入ると味噌はお店で買うものとなり、麹屋の数はみるみる減っていった。

中庭から差し込む光が美しい作業場
中村屋の麹づくりは夫婦二人三脚。その時々で手に入りやすい安心・安全な米を選び蒸し上げ、作業台に移し手作業でほぐしていく。中庭から差し込む光と敷き詰められた米の白さが、まるで初冬のキラキラ光る新雪の美しさだ。30℃ほどに冷めたところで麹菌をまぶし、杉板でできた升に入れ積み重ね、麹室で発酵させる。機械による製造が増える中、中村屋ではこの『蓋製法』と呼ばれる昔ながらの作り方を続けている。
「麹は生き物です。麹室の温度は30℃、湿度は90%を目安に、成長の過程で変えていきます。温度と湿度は天井にある2つの空気口の開け閉めで調整するのですが、外気温や天候によって急激に変わってしまいます。体で感じつつも30分に一度は室に入り計器でチェックするんです」。調整のタイミングをわずかでも間違えると、思ったとおりの麹に仕上がらない。お客さんに渡せない(売ることができない)わけではないが、100点満点の麹を知っているからこそ「がっかりする」のだという。

棚で発酵が進まないよう気にかける
妻の真咲さんは「私自身、麹を通じてたくさんの方々と知り合いとても世界が広がりました。中村屋は麹を作り売ることを生業としていますが、その間の会話で得た古くからの知恵や斬新なアイデアを、伝え広げることがもう一つの使命であり、中村屋の存在意義であると感じています」と、日々SNSで麹の魅力を発信している。

注文を聞いて量り売りするスタイル

天野理恵さんお手製大中寺いものポタージュと天ぷら
(ライター/reiko)
<DATA>
■中村屋麹店
住所:駿東郡清水町新宿25
TEL:055-975-0301



 シェア
シェア ポスト
ポスト LINEで送る
LINEで送る