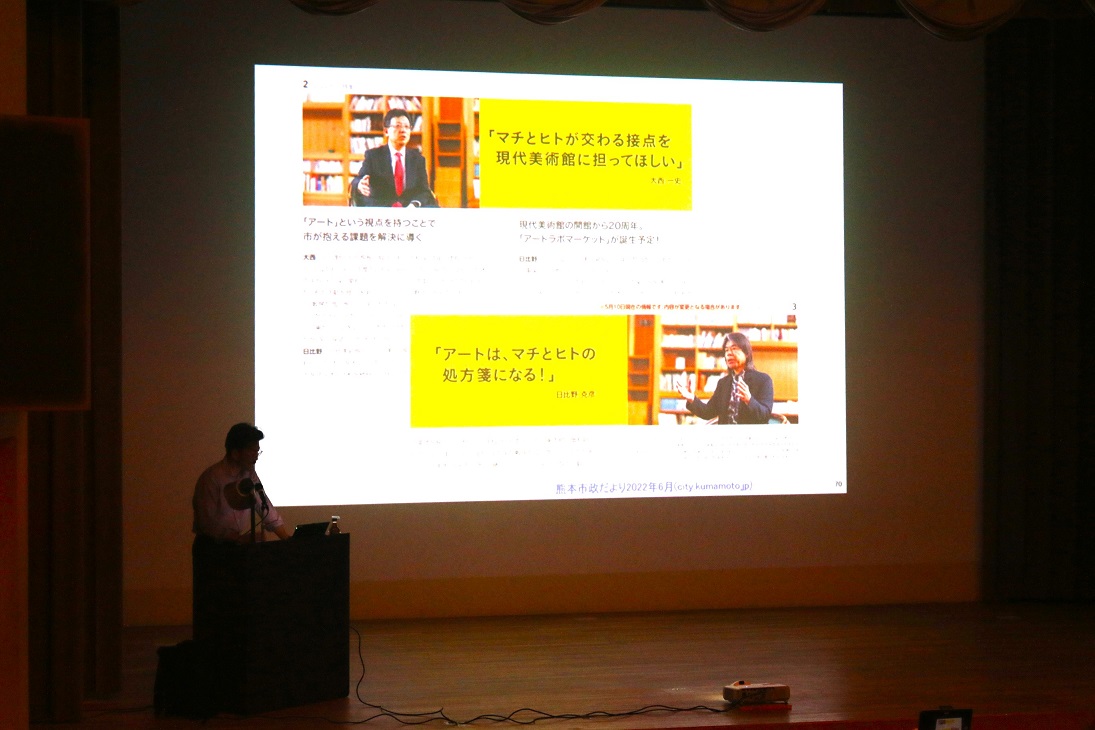
67年ぶりに改正された博物館法が2023年度から施行されたことを受け、県内の博物館・美術館の役割はどう変化するのか。講習会は地域のミュージアムの未来像を考える機会となった。
文化庁博物館支援調査官の中尾智行さん、県教育委員会社会教育課の深谷一真さん、県立美術館の木下直之館長が登壇した。特に印象に残ったのが文化庁の中尾調査官が「新しいミュージアムの形」として掲げた「新しい価値を社会と共創する」という言葉だ。
政府による思想統制で「文化」の幅が狭められた明治から昭和初期まで。国や地方自治体によって文化・芸術の啓蒙普及が進められた太平洋戦争後から平成前期まで。市民主体の自立的な文化活動が重視されるようになった平成後期から令和まで。日本社会における文化・芸術の位置づけの変化を受けて、文化芸術基本法、文化財保護法に代表される関連法が整備されていく。中尾さんはその過程を分かりやすく説明した上で、こう締めくくった。
「 重要文化財、国宝のような、基準を設けた、定まった価値をしっかり共有していくと同時に、(博物館の)利用者や情報の受け手の相対的な価値をどう作っていくか。 保存と活用の循環の中で価値を創り出す視点が必要になる」
2020年代の博物館・美術館は、地域連携とクリエーティビティーが一層求められるのだと、改めて認識した。(は)

県教委社会教育課の深谷一真さんは、県内の登録博物館数などのデータを示した。「全国的に見ても施設数が多い県だと思う」
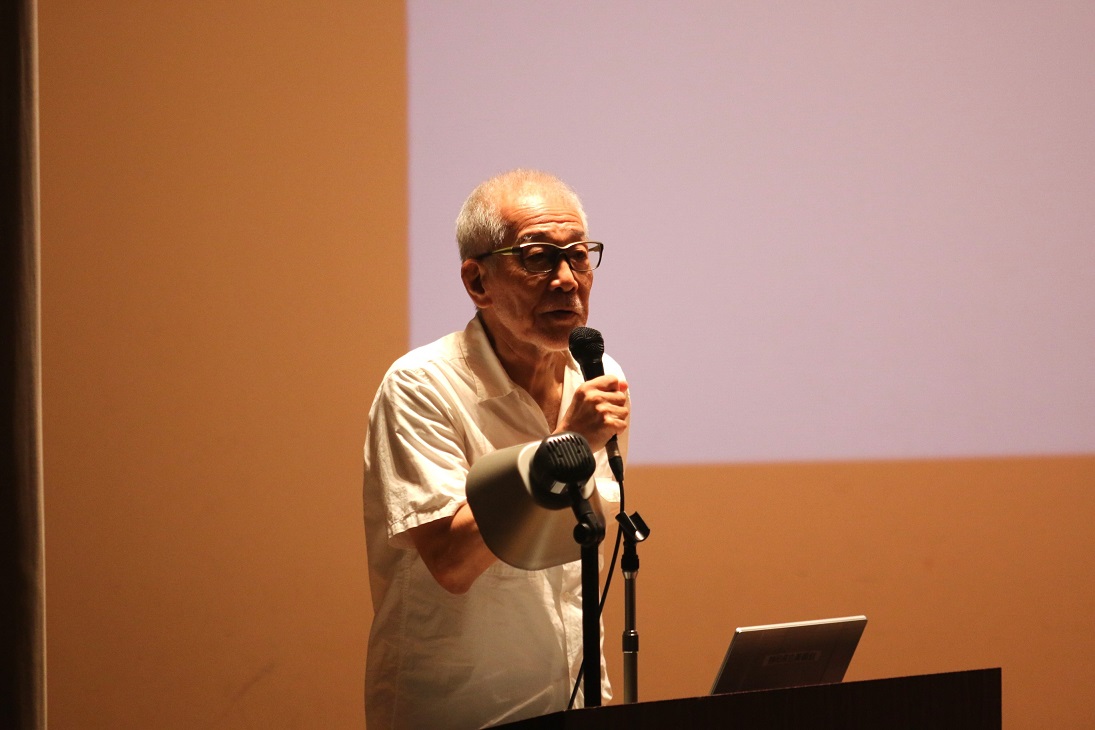
県立美術館の木下直之館長は「文化資源」という言葉を自身の経験を交えて読み解いた。「文化資源、文化観光、観光資源という三つの言葉の関係を考えることが、状況を理解する上で重要」



 シェア
シェア ポスト
ポスト LINEで送る
LINEで送る


































































