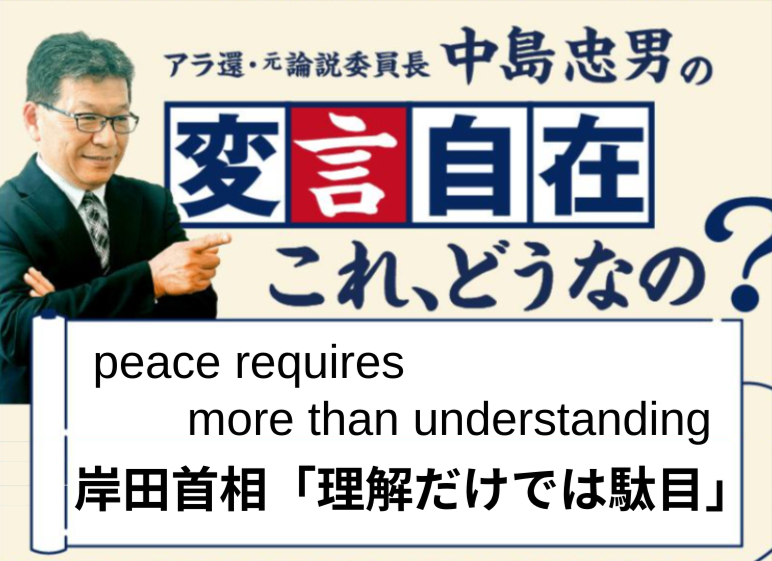 岸田文雄首相の外交政策が「とても優れている」との評論が静岡新聞に掲載されました。作家で元外務省主任分析官の佐藤優氏が記した4月19日付朝刊の「論壇」です。内政で失態が続き、岸田政権の支持率は低迷状態を脱しきれませんが、外交では的を射た政策を推進していると指摘。バイデン米大統領との首脳会談で岸田首相は、国際情勢を踏まえた現実主義的外交政策を展開したと評価しました。
岸田文雄首相の外交政策が「とても優れている」との評論が静岡新聞に掲載されました。作家で元外務省主任分析官の佐藤優氏が記した4月19日付朝刊の「論壇」です。内政で失態が続き、岸田政権の支持率は低迷状態を脱しきれませんが、外交では的を射た政策を推進していると指摘。バイデン米大統領との首脳会談で岸田首相は、国際情勢を踏まえた現実主義的外交政策を展開したと評価しました。米国は自由と民主主義の旗を掲げ、同盟国を率いてきました。しかし、地域間紛争が激化し、ロシアと中国は覇権を強める一方、経済分野で各国の相互依存は強まるばかり。国際政治情勢は多極化し、理念を前面に出した外交で同盟国を率いることの困難さが増しているのです。佐藤氏は日米首脳会談の共同声明に「価値観」「民主主義」の言葉が出てこなかった点に着目し、米国の影響力が後退していると読み解きました。国際情勢を理解するのに役立つヒントを提供しています。
外交に必要な「覚悟」
このコラムのタイトルにある英文は日米首脳会談の翌日、岸田首相が米国連邦議会上下両院合同会議で「未来に向けて-我々のグルーバルパートナーシップ」と題して行った演説の一説です。And yet we also know that peace requires more than understanding. It requires resolve.
=しかし、今の私たちは、平和には「理解」以上のものが必要だということを知っています。「覚悟」が必要なのです(外務省訳)
岸田首相は世界の安定と繁栄をけん引してきた米国の功績を高く評価した上で、平和の尊さやあるべき姿を理解するだけでは不十分だと指摘しました。日米両国が人権の抑圧、政治的な自己決定権の否定、デジタル技術で人々を監視し続ける社会を排除するために行動することの必要性に言及し、それが「世界中の未来世代のための大義であり利益」と強調しました。そのために覚悟が必要だと。
佐藤氏はこの発言を受け、軍事力に裏付けられた外交によってこそ腹を割った本音の対話が実現すると解釈します。この点は評価が分かれるかもしれません。
サプライチェーンの実像
価値観を掲げる外交戦略が奏功しにくくなった要因である経済の相互依存。それを理解するため、私たちが愛用するスマートフォンなど、日常生活を支える電子機器がどのように製造されているのかをたどってみましょう。キーワードは「サプライチェーン」。ものづくり産業で、材料調達から生産、物流、販売など消費者に品物が届くまでの一連の流れを意味します。「カリフォルニアでデザインされたApple製品。作っているのは、世界中の人たち」。米アップル社はコーポレートサイトで、50以上の国と地域で数千の事業者と数百万の人々により自社製品の製造、配送、修理、リサイクルが成り立っていると説明。人権、環境、安全に配慮し、サプライチェーンに関わる人やコミュニティーを支え、地球を守る取り組みを進めていると記しています。
このように資本や労働力、サービスが国境を越えて行き来し、国際的分業が進展しています。経済活動のグローバル化と称し、サプライチェーンは国境をまたぎ複雑さを増しています。国境や政治体制は国際政治で重要な意味を持ちますが、サプライチェーンの議論に限れば供給網の維持で考慮すべき事項の一つと言える状況になってきました。
中国はアジア地域で覇権主義的な実効支配を拡大し、日本政府は警戒感を高めています。米国内でも中国脅威論が隆盛です。ところが、日本の外務省がまとめた中国経済概要(2022年)によれば、中国の最大の貿易相手国は米国です。日本は韓国に次いで3位。また、日本にとって中国は米国、オーストラリアに次いで第3位の投資先。中国には日系企業の拠点が3万1324拠点もあり、日系企業の海外拠点数で中国は第1位です。
ロシアのウクライナ侵攻を機に、欧米は世界のエネルギー市場からロシア産の天然ガスや原油を締め出す経済制裁に踏み込み、国際金融決済市場からの退出を迫りました。やがてロシア経済は疲弊し侵略行為をやめるだろう-との期待がありました。現実はどうでしょう。中国やインドは安くなったロシア産原油を買い増しました。そればかりか、ロシアの液化天然ガス(LNG)は今年1月、欧州連合(EU)向け輸出量が約160万トンで、ウクライナ侵攻前の22年1月比で3割増加しています。
民主主義とてアラカルトの一つ
国際社会で「民主主義陣営か権威主義陣営のどちらに与(くみ)するのか」の二者択一は大した意味を持たなくなってきました。安全保障では米国を頼り、経済では中国やロシアとの親密な関係を維持したいと考える新興国、途上国はたくさんあります。歴史ある超大国といえども、自由と民主主義の理念を語っているだけで実利をもたらさなければ仲間と思っていた国にそっぽを向かれる-。外交の実像は私たちの社会生活と似通った面もあるのです。国際政治の厳しさに思いを致せば、茶の間で見聞きする難解なニュースがちょっと身近に感じられるかもしれません。中島 忠男(なかじま・ただお)=SBSプロモーション常務
1962年焼津市生まれ。86年静岡新聞入社。社会部で司法や教育委員会を取材。共同通信社に出向し文部科学省、総務省を担当。清水支局長を務め政治部へ。川勝平太知事を初当選時から取材し、政治部長、ニュースセンター長、論説委員長を経て定年を迎え、2023年6月から現職。



 シェア
シェア ポスト
ポスト LINEで送る
LINEで送る




































































