
(橋本)性同一性障害の人が戸籍上の性別を変更する場合、生殖能力をなくす手術を事実上求める「性同一性障害特例法」の規定「生殖能力要件」が憲法に反するかどうかが争われた家事審判で、最高裁大法廷は25日、規定を違憲、無効とする決定を出しました。
(山田)橋本さん、本当にゼロからちょっと伺いたいんですけども、今回のこの裁判ってどういう裁判だったんですか。
(橋本)性同一性障害特例法は2004年7月に施行されました。この法律によって、性同一性障害の人のうち特定の要件を満たす人については、家庭裁判所の審判で法令上の性別の取り扱いと戸籍上の性別記載を変更できるようになりました。
特定の要件というのは5つあります。①18歳以上である②現に婚姻していない③未成年の子がいない④生殖腺がないまたは生殖腺の機能を永続的に欠く⑤性器に係る部分に近似する外観を備えているという5つです。
例えば、結婚してる方が途中で女性から男性に変わってしまうと、男性と男性の同性婚になっちゃいますよね。そうすると、法律的にまだ認められておらず、そこで秩序に混乱が生じますので、現に婚姻していないということが要件に入っています。また、性別変更の後に子供が生まれた場合に混乱を避けるという意味で、生殖線の機能を永続的に欠くという先ほどの4番目の要件があったりします。4番目と5番目の要件は、多くの場合、事実上手術をしないと要件を満たさないことがあります。
(山田)今回の最高裁の判決ですけども。
(橋本)5つの要件のうち4番目の「生殖腺の機能を永続的に欠く」という要件についてなんですが、申し立てたのは西日本に住む、戸籍上は男性で性自認が女性という社会人の方です。手術は身体的に負担があるので、手術せずとも性別変更を認めてほしいと求めた審判があり、2020年に家裁と高裁で性別変更が認められず、最高裁に特別抗告をしていたということです。
最高裁は、10月25日に15人の裁判官による大法廷での審理で、手術を強いる生殖能力要件は憲法違反で無効だと決定しました。
(山田)手術しなくていいよってことになったんですね。
(橋本)最高裁によって法令が違憲と判断されたのは12例目になって、特例法については今回が初めてでした。
(山田)珍しい判決だったわけですか。今回のポイントは。
(橋本)最高裁は2019年に小法廷で、この規定が「現時点で合憲だ」っていう判断を示していました。4年経ってそれを覆した理由として、一つには、特例法が施行された2004年から19年経過し、1万人以上が性別変更して性同一性障害への社会の理解が進んでいることを挙げています。
特例法の施行当時は、性同一性障害の治療を段階的に進めていく考え方だったようです。その最終段階で性別適合手術を受けて治療が完了したという形になるということで、それに合わせた法律だったんです。
しかし、その後いろいろな事例があって、性同一性障害の症状というのは多様で、どのような身体的治療が必要かは、患者によって異なるということになってきました。なので一概に、手術をしたから治療が完了ということではなくなり、その辺りの医学的なことも変わってきたので、そうした状況を踏まえての今回の最高裁の決定だったわけです。
2004年施行のこの法律の内容では、性別変更するためには、手術をしたくなくてもしなきゃいけないという状況に追い込まれる人がいるわけです。
(山田)手術して性別を変えるか、もしくは手術をしないで性別を変えないかしかなかった。
(橋本)最高裁はそれを「過酷な二者択一だ」というふうに言っています。そういう理由で、これは違憲だと。憲法13条で「自分の意思に沿わない形で身体を傷つけられることはありません」ということを保障しているのに、それが実質的に守られていないから、これは違憲だという判断になったということです。
(山田)手術にやっぱり、抵抗があるわけですもんね。
(橋本)簡単な手術ではないし、費用も高額になるようです。経済的な理由から手術したくても受けられないという人もいるし、親からもらった体に傷を付けたくないということで手術できない人もいます。性同一性障害だから性を変えたいと思っていても、思いとどまってしまうような事例があり、そういう状況に追い込んでいる今の法律のあり方は適切ではないんじゃないかということで違憲と判断されました。
(山田)なるほど。
(橋本)ただ、今回審判を申し立てた方は、手術しないで性別変更を認めてほしいと求めていたわけですが、最高裁の判断では認められませんでした。
生殖能力の要件に関しては手術しなくても認められると決定したのですが、「性器の外観に関する要件についてはまだ審理がちゃんと終わってないのでそれを高裁でもう1回審理し直してください」ということで差し戻したんです。なのでこの方の性別変更もまだ認められてない状況です。
公衆浴場などの運営については「付帯意見」も
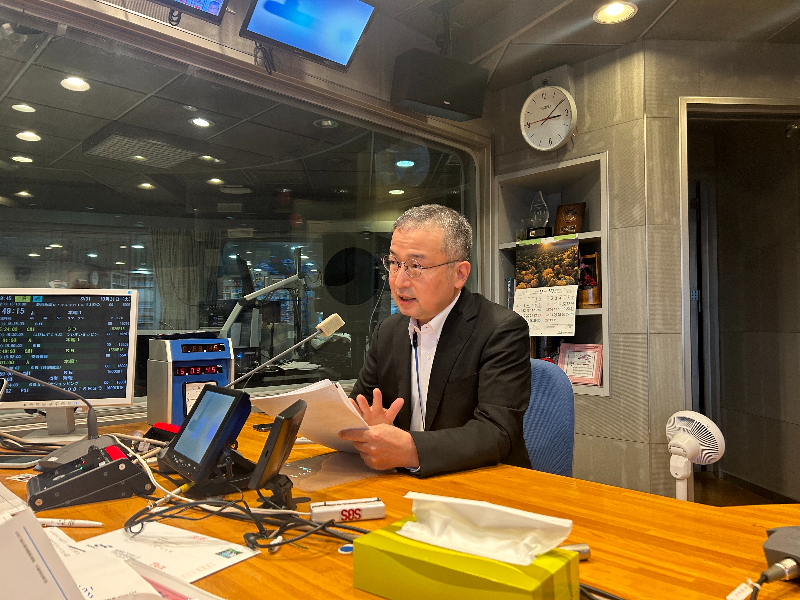
(山田)一般的に今回のこの裁判でどうなのって思うのは、心は女性で、でも外見は男性という方が、この外見のまま女風呂や女性の施設に入っていいのかっていうところです。かなり皆さん不安があると思うんですが。
(橋本)そういう議論はもう起こっています。この判決に対して「それはおかしいじゃないか」という意見も出てますし、この決定が出る前に、当事者団体が「手術要件は合憲だと判断してほしい」という要請をしているんですよ。性同一性障害ではない方、特に女性には、今言われたような不安を抱く人がいるので、当事者の方たちが生活していく上で拒絶反応を示されたりすると困りますよね。なので、そういうことも考えて申し入れされたんだと思います。
ただ、4つめの要件が違憲と判断されたことを前提にすると、自分の意思に沿わない手術というのは憲法上認められないということであの決定を下したわけですから。外観要件に関しても、この後の審理で違憲だという判断になる可能性はあると思います。まだどうなるかわかりませんけどね。
女風呂に、性同一性障害の方で体が男性の方が入ってくることがあるじゃないかという心配というのは結構聞くんですが、これについては、この決定の中に裁判官が「付帯意見」というのをつけてまして。
例えば公衆浴場については、現状でも、その施設がどういう運用するかを決めて運用しています。つまり外観上、男性、女性に分けているわけですよね。そうした運用というのは、この判決が出たからといって、変える必要はありませんよということです。
(山田)ある意味、施設に判断を任せると。
(橋本)女性の方たちが、男性の体をした方が入ってくるんじゃないかという心配をしなくても今まで通りに安心してお風呂に入れるような、そういう運用は可能ですよということを言ってるわけですね。
その点は、やっぱり理解されてない部分もあります。違憲判断が出たことで、これから法律を変えなくてはいけないので、国会でそういうことも議論されると思います。
なので、新しい法制度を作るときに、そういう問題についてもちゃんと議論して、今言ったように「施設の判断で外観で男女を分けます」ということもちゃんと認めるということを明確にする必要もあるのではないでしょうか。
そういうことが、性同一性障害の方の新たな法制度を社会が受け入れていくということに繋がると思うんですね。
(山田)ちゃんと決めてもらって明確にしていくっていうのが必要ですし、我々は受け入れていくことが大事ですね。
(橋本)よくある誤解では、例えば私は男性ですが、「明日から女性だ」って言えば女性になれるんじゃないかって思っている方もいるかもしれません。
けれども、この法律で性同一性障害の人の定義というのは、2人の専門医が診断をし、性同一性障害だと判断をした方ということになっていますので、自分が「性別を変えます」って言えば認められるということではありません。そういうこともしっかり啓発をしていくことが大事なんじゃないかと思います。
(山田)なるほど。というわけで、ちょっと不安だったり、どうなのかなと思うところが、解説していただいてよくわかりました。今日の勉強はこれでおしまい!



 シェア
シェア ポスト
ポスト LINEで送る
LINEで送る



































































