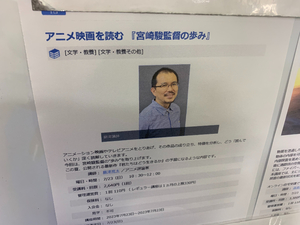SBSラジオ「TOROアニメーション総研」のイチオシコーナー、人気アニメ評論家の藤津さんが語る『藤津亮太のアニメラボ』。今回はアニメーションの美術監督で、2023年8月19日に亡くなられた山本二三さんについてお話を伺いました。※以下語り、藤津亮太さん
宮崎監督にも実力を認められた努力の人
山本さんは1953年長崎県の福江市(現五島市)で生まれました。中学校卒業後は仕事の傍ら、定時制高校へ通いながら働いた後、さらに夜学のアニメーション専門学校に行き、そこから『サザエさん』の美術をするようになったそうです。その後、武蔵野美術大学短大の定時制にも通っています。自力で少しずつ勉強しながらアニメーションの世界に入っていったんですね。そして、日本アニメーションと接点ができて『くまの子ジャッキー』という1977年の作品で、美術監督の伊藤主計さんにつくことになりました。伊藤主計さんは『アルプスの少女ハイジ』や『赤毛のアン』などの美術を担当された方で、日本のアニメーション美術の一つの大きな流れを作った方です。山本二三さんの最初の師匠ということになります。
同時期、宮崎駿監督は『未来少年コナン』の準備をしていました。ところが第1話が本格的に始まる前に、宮崎監督と方針が合わなかったのか、美術監督がいなくなっちゃうんです。そこで山本さんが送り込まれました。山本さんは徹夜がないことを条件に受けたのですが、初日から徹夜だったようです。当時のアニメはかなりめちゃくちゃなスケジュールで作っていましたからね。
70年代のアニメでは、まだまだ背景に美術を追求しているものは多くありませんでした。そんな中にあっても、宮崎監督の求めるレベルは高かったので、山本さんもものすごく苦労したそうです。でもその仕事ぶりを買われ、『ルパン三世 カリオストロの城』(1979年)でも、要所要所の細かい部分や、特殊なテクスチャー感がいるところは、山本さんが呼ばれています。
その後も例えば『もののけ姫』(1997年)では屋久島などをモデルにしたシシ神の森を担当しました。美術には当人の出身地の雰囲気が出るという考え方があるようで、五島出身の山本さんは、湿度の高いシシ神の森などを中心に担当するようになったそうです。
高畑勲監督との接点は『じゃりン子チエ』(1981年)と『火垂るの墓』(1988年)が大きな仕事となりました。『じゃりン子チエ』は原作があるのですが、それはペン画のイラストに水彩でタッチを入れたくらいのシンプルな絵です。なので、山本さんの画業の中では引き算の度合いが高く、ある意味、ちょっと異色なお仕事といえます。ただ、すごくシンプルな線画でも質感はリアルで、そこに魅力があります。
リアリティを追求したアニメーションを描く
山本さんは、その空間に人を引き込みたくなるような背景を描く方で、例えば『火垂るの墓』の美術にはそれがすごく現れています。山本さんは「生きていた人が死んでしまう話だから、部屋の中にそういった人がいた雰囲気を描く必要がある」ということで、例えばタンスがあったら、使い込んでいたタンスの取っ手が白くなっている様子まで描いて、人が暮らしている生活感を浮かび上がらせています。
また、細田守監督の『時をかける少女』(2006年)では、いろんなところで山本さんが描いた雰囲気のある雲が登場しています。夏の話なので、山本さんの雲がほしいと参加をお願いされたようです。
『時をかける少女』の背景を見ると、密度感をきっちり描き込んであって、本当に1個ずつのものに愛情が込められているのがわかります。雲だけでなく、理科実験室のフラスコやビーカー、雑貨屋の奥に並んでいる商品など。雰囲気がちゃんと出るようにしたいという思いがすごくあるんですね。
高畑監督が山本さんの美術のことを「個々のものに愛情を注いで、ものに緻密な存在感を与えてくれる」「リアリティのある空間に連れていく」と言っていますが、それは『火垂るの墓』を経て『時をかける少女』につながるお仕事を見るとよくわかると思います。
また近年は、故郷・五島のふるさと大使も務めており、「五島百景」として五島のいろんな風景を描いています。風景を愛しているのが伝わってくる綺麗な絵が多いです。
山本さんはおそらく、日本のアニメーションで緻密な精度で背景を描いて、それが魅力であることを達成した極初期の人ではないかと思います。
実際の東京を舞台にした『さらば愛しきルパン』(1982)という作品があるんですが、当時の新宿から高円寺にかけてが非常にリアルに描かれています。またそれに続く『名探偵ホームズ』(1984)の初期制作話数でも、ロンドンの石畳のある風景や室内などの壁紙が徹底的に描きこまれ、作品の雰囲気作りを支えています。これらはやはり山本さんの美術がないと成立しなかった作品だろうなと思います。
(SBSラジオ 2023年8月21日放送)



 シェア
シェア ポスト
ポスト LINEで送る
LINEで送る