コーヒーから誕生したお茶「カスカラティー」
私達が普段飲んでいるコーヒーは、コーヒーチェリーと呼ばれる実の中の種を焙煎してコーヒー豆として利用していますが、その周りを囲んでいる果肉と皮の部分がカスカラと呼ばれています。

「大量に廃棄されるカスカラを何かに利用できないか・・・」
そんな問題を解決すべく、静岡文化芸術大学で2020年4月からスタートしたプロジェクトが「カスから生まれるプロジェクト」。学生さん達がコスタリカのフェアトレードコーヒー農家さん達と協力しながら誕生したのがオリジナルの「カスカラティー」です。
ということで今回は、静岡文化芸術大学のフェアトレードサークル「りとるあーす」の皆さんと一緒に、フェアトレードや環境問題について一緒に学んでみましょう!

フェアトレードタウン、フェアトレード大学
更に、浜松市内にある「静岡文化芸術大学」は、2018年の2月にアジア初のフェアトレード大学に認定され、国内でも特にフェアトレードの推進に積極的に取り組んでいる大学です。

フェアトレードとは?
開発途上国の農家や手工業者など、立場の弱い小規模生産者の自立と生活改善の為に公正な価格で取引を行う取組のことです。女性の手工芸品などの生産をはじめ、現在はチョコレート、バナナ、コーヒー、紅茶、ワインなどの食品にも広がっています。
(※静岡文化芸術大学HP参照)
近年では貧困問題だけでなく、カスカラティーのように現地の環境問題に配慮した問題も重要視されているそうです。

日本のほうじ茶からきたアイディア
カスカラティーの飲み方として、現地ではカスカラを焙煎せずにそのまま利用することも多いそうです。しかし、実際に飲んでみると酸味が強く日本では飲み慣れない味でした。
「美味しくて売れる商品にしないと、廃棄が出て意味がない・・・。」
酸味を抑える為に牛乳と合わせたり、お茶漬けにしたり、梅酒と割ったり。一体どうすれば日本で美味しく飲むことができるのか・・・、試行錯誤の日々が続きます。
そんな中、お茶屋さんからヒントを得たのが「焙煎」。日本のほうじ茶のように、焙煎することで酸味を抑える手法に目を付けます。
現地から乾燥した状態で送られてくるカスカラを、県内の企業と協力しながら焙煎加工。誰もが納得する味を見つけ出し、日本初の焙煎カスカラティーが誕生しました。

学生の専門分野を生かした商品開発
静岡文化芸術大学にはデザイン学部と文化政策学部があり、自分達の専門分野を生かし文化とデザインのそれぞれの側面を実践できる学生ならではの、みんなの想いが形になった商品でもあります。

気になる!カスカラティーの味
見た目はまるで紅茶みたい。焙煎しているのでコーヒーに近い芳ばしい香りを持ちますが、実際に飲んでみるとコーヒーとはほど遠くフルーティーな味わいです。「コーヒーチェリー」と呼ばれるくらいなのでフルーツのような甘味も感じ、とても飲みやすい味です。アイスでもホットでも、いつものお茶のように楽しむことができます。
アンケート結果では、焼き芋や黒糖のような味、という意見も出たそうです。

コーヒーに比べてカフェインの量が少ないので、飲む時間を選ばないのも大きなポイントです。

コロナに負けない!積極的な販売促進活動
それでも、緊急事態宣言やまん延防止が解除されている時期にはイベントにも積極的に参加し、精力的に販売促進活動を続けます。その成果もあり、今では関心を持つ人がどんどん増え、構内の生協に買いに来てくれるお客様も多いそうです。
活動を通してたくさんの人に出会えることも楽しみの一つだそうで、そんなまっすぐでポジティブな学生さん達の想いからも、より商品への魅力を感じます。

フェアトレードを学ぶ学生からのメッセージ
三ツ矢ゆりえさん(3年)からのメッセージです。
フェアトレードに興味があっても、何から取り組めばいいか難しく考えてしまいがちですが、商品について一緒に考える、選ぶ、購入してみるだけでも、世界を変える行動の一つに繋がることを教えてくれました。

フェアトレードに興味を持つきっかけに
「小学生の頃から絵本の『もったいないばあさん』が好きで、当時からエコバックを持っていました。ケチなだけかもしれないんですけど(笑)。今思えば、そういうのがきっかけでフェアトレードに関心を持ったのかもしれないです。」
学生の皆さんにフェアトレードに興味を持ったきっかけを聞いてみると、幼少期の身近なものから現在に繋がっていることがわかりました。

なぜこの商品が誕生したのか、どんな人が関わっているのかなどお家でも子ども達と話しながら、フェアトレードについて触れるチャンスをどんどん増やしていきたいですね!
(写真提供:静岡文化芸術大学)



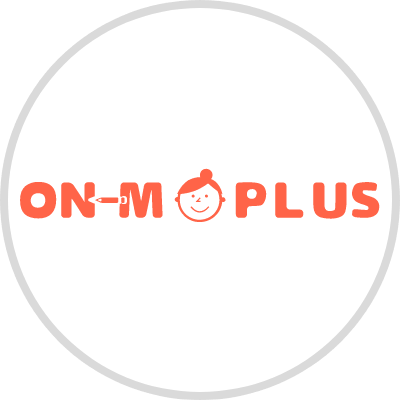
 シェア
シェア ポスト
ポスト LINEで送る
LINEで送る





































































