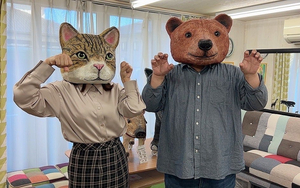ゲスト展示として、静岡市出身の彫刻家掛井五郎さん(1930~2021年)のさまざまな手法による作品が並んでいる。静岡市民文化会館の「南アルプス」、静岡県立美術館屋外彫刻プロムナードの「蝶」、母校静岡市立高に設置されている「バンザイ・ヒル」など、よく知られる重量感のあるブロンズ作品とは異なる、奔放な発想と鮮烈な表現の数々に圧倒される。
天井が高い展示室に入ると、見上げるような巨大な絵画が圧倒的な存在感を放つ。監修者の白井嘉尚静岡大名誉教授によると大きさは「300号」とのこと。横2メートル、高さは3メートル近くあるのではないか。グランシップの搬入用エレベーターにぎりぎり収まり、なんとか6階に運んだという。

筆者はさまざまな場所で掛井五郎さんの作品に接しているが、これほど大きな作品は見たことがない。2021年に静岡県立美術館で行われた「STOR!ES(ストーリーズ)」展に出ていた「母の存在」(1991年)も大きかったが、高さ2メートル30センチほどだ。
1990年代に描かれた今回展の作品群は、群馬県桐生市に居を移した時期に制作されたものだ。アトリエの環境、条件がこうした大作に向かわせたのだろう。ドローイングに近い作品で、構図云々より直感的に描きたいものを置いたという印象が強い。掛井五郎さんらしい、形を崩した人体がそこここに見えるが、緑の野辺と切り妻屋根の家屋、湖を描いた風景画もある。
緻密な計算はないのだろうが、少し距離を取って作品を眺めると、画面全体の少し沈んだような色彩は共通するものがある。これぞまさしく彼の「作家性」なのだろう。

昨年末から今年始めにかけて静岡市清水区のフェルケール博物館で開かれた企画展「掛井五郎の仕事」でも紹介されていた「紙彫刻」も味わい深い。トイレットペーパーの芯や円柱状に丸めた紙で作られた人間の顔。今回展でも200点ほどが林立している。壮観だ。
構想に検討を重ねて顔を作るというより、手を動かしていたら自然に表情ができてしまった、という趣だ。若い頃よりは体の自由がきかない最晩年に、身の回りにある素材からこのような手法を切り開くクリエイティビティーがまぶしい。そしてそれは、「誰もがWonderfulアート」展のもう一方の主役である、県内特別支援学校の児童・生徒たちの作品と、明らかに共鳴している。
体を使って何かを生み出す。この行為そのものが「価値」である。展覧会に通底するメッセージを、比類なきこの彫刻家はずっと昔に先取りしていたのではないか。
掛井五郎さんの作品はグランシップ1階エントランスやショーウインドーにも展示されている。
<DATA>
■グランシップ 誰もがWonderfulアート
会場: グランシップ 6階展示ギャラリー
住所:静岡市駿河区東静岡2-3-1
入場料:無料
会期:10月5日(日)まで
開館時間:午前10時~午後5時

特別支援学校児童・生徒の作品から。筆者が心打たれた「チュンチュンとり」。浜松みをつくし特別支援学校高等部1年の喜納悠水さん作



 シェア
シェア ポスト
ポスト LINEで送る
LINEで送る