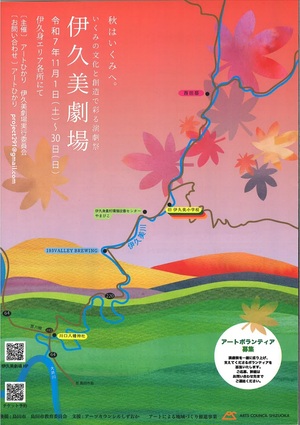.png)
みなさん、こんにちは。編集局紙面編集部の遠藤竜哉です。
先日、アクトシティ浜松でイタリアの名門「パレルモ・マッシモ劇場」による引越し公演がありました。演目は、数あるイタリアオペラの中でも最も人気のある作品と言ってよいでしょう!ジャコモ・プッチーニ作曲「ラ・ボエーム」です。
書かずにはいられない!と思える感動的な公演でしたので、全力レポートします!出演者に取材した「裏話」もありますので、ぜひ最後までお読みください。
プッチーニの最高傑作
さて、この「ラ・ボエーム」。皆さんも、どこかで名前を耳にしたことがあるのではないでしょうか。
「ボエーム」というのは、フランス語で「ボヘミアン」の意。自由奔放に生きた芸術家の卵たちのこと。舞台は1830年頃のパリ。ざっと言えば、屋根裏に下宿する詩人ロドルフォと、部屋に火を借りにきて出会ったお針娘ミミとの恋物語。
ミミは肺病を患っていて、最後に死んでしまいます。芸術家仲間である画家マルチェッロや、その元恋人ムゼッタら、2人を取り巻く登場人物も個性豊か。クリスマス・イブから始まる全4幕のストーリーの中で、プッチーニの美しい音楽が奏でられます。
1896年に大指揮者トスカニーニの指揮で、イタリア・トリノで初演されました。プッチーニの最高傑作の一つと言って間違いないでしょう。
プッチーニの名曲の数々
プッチーニには、他にも「蝶々夫人」「トスカ」「トゥーランドット」など頻繁に上演される有名なオペラが複数ありますよね!それぞれの作品に、主役級の歌手の見せ場となるような有名な曲(アリア)が散りばめられ、お客さんも、それを楽しみに劇場へ足を運びます(ですよね??)
特に有名な曲としては、
・「蝶々夫人」…ある晴れた日に
・「トスカ」…歌に生き、恋に生き/星は光りぬ
・「トゥーランドット」…誰も寝てはならぬ
などなど…。
「私のお父さん」なら知っている!という方もおられるでしょう!
これは「ジャンニ・スキッキ」というオペラの中で歌われます。ピンとこない方も、音源を聞けば「あー、これね!」と分かるはずです。
メロディーの宝庫「ボエーム」
そして「ボエーム」!気前よく、有名な曲が三つも含まれています。
第1幕のロドルフォとミミが出会う場面で歌われる、ロドルフォの「冷たい手を」、ミミの「私の名はミミ」。そして、第2幕、夜の盛り場でムゼッタが“元カレ”であるマルチェッロの気を引こうと歌う「私が町を歩くと」。気の強いところがあるムゼッタが、私ってこんなに魅力的よ!と周囲にアピールしているのですね。
2時間弱のオペラ全体の中でも、第2幕は最も舞台が華やかで、音楽的にも一つの頂点を迎えます。オペラって外国語だし、長いし、何がそんなに良いのだろうと思う方もいらっしゃると思いますが、この第2幕のような華やかな舞台を体験すると、日常の些細なことは忘れてしまいます…。
もう一つ聞きどころは、第3幕のフィナーレ。
ミミの肺病を知って「貧乏な自分からは離れた方が良いのでは」と考えたロドルフォが、ミミに別れを告げるその背後で、よりを戻したマルチェッロとムゼッタがまた喧嘩しています。
これが、見事な四重唱になっていて、私は、プッチーニが世に残した最高の音楽の一つだと思っています。この美しさは比類がありません…。
ちょっと脱線して歴史の話
ちなみに、1830年といえばパリ7月革命。以前ご紹介した、ベルリオーズの「幻想交響曲」が初演されたのが、この年。この革命に刺激されたポーランドで独立を目指すワルシャワ蜂起が勃発し、ロシアに鎮圧されてしまいますが、この報に接したショパンが激しい感情をぶつけ作曲したのが、かの有名な「革命のエチュード」です。
この後、ポーランドではロシアによる粛清が待っていたわけですが、この時にウラル地方に流刑された一人が、20世紀ソヴィエトの大作曲家ショスタコーヴィチの曽祖父だそうです。
このあたりの話は、桐朋学園大・西原稔先生の「クラシックで分かる世界史」(アルテスパブリッシング)という本に詳しく載っていますので、ご興味ある方は読んでみてください。
オペラ「ボエーム」自体はお芝居ですが、舞台となった実際の華やかなパリの街は、同時に、このあと数十年に及びヨーロッパ各地に連鎖する革命の「震源地」でもあった、ということですね。
クラシック音楽から切り取る世界史!本当に面白い!
今回の公演、歌手もオケも歌いに歌っていました。
さてさて、話を今回の公演に戻します。新型コロナ禍で海外劇場の来日が全国的に停滞していましたので、今回の引越し公演は特別感がありました。イタリアから訪れた歌手たちの素晴らしさは言うまでもなく、オケの伸びやかな演奏も印象的でした。
劇場の楽団だけあって、歌手にぴったり付けるのが本当にうまい!マエストロ(指揮者)も、抑制の効いたピアニシモから、全開のエスプレッシーヴォまで、ダイナミクスの幅が見事。
まるで、駿河湾の底から富士山頂まで行ったり来たりするような、レンジの広さでした!!
子役で「ジュニアクワイア浜松」が出演
白眉の第2幕では、夜の雑踏の場面を盛り上げる子供たちの役として、地元浜松の合唱団「ジュニアクワイア浜松」が出演しました!!控えめに言っても、ブラボーでした!
小学5年から高校3年までの25人。周囲は体の大きなイタリア人の歌手ばかり。目の前で本場のオケが鳴っているという環境下でしたが、物怖じする様子もなく、舌を巻きました。
また、児童合唱とは別に、第1〜3幕に登場するウエイター役として、2人の同団メンバーがエキストラ出演しました。歌も演技も、相当入念に作り込んだ印象でした。

しかし!
驚くことに…
なんと!!!!!
ほぼ、ぶっつけ本番だったそうです!!!
えー!
本公演の主催者である浜松市文化振興財団やジュニアクワイアの指導員の方々に話を聞いたところ、練習が始まったのは4月下旬。通常練習の傍ら、ボエームに割くことができたのは限られた時間だったそうです。
指導員の方々がオケ伴奏をピアノに置き換え、児童合唱のパートをイタリア語で分かりやすく歌唱した「お手本」の練習音源を手作りし、総力戦で臨んだ、とのこと。
舞台上での動きに関して書かれた指示書などは事前にあったそうですが、全国公演のため、前日までオケは群馬県高崎市におり、本番の舞台環境は当日のみ。
しかも実際には、最低限の確認事項だけで本番に臨んだそうです。事情を感じさせない舞台を実現したジュニアクワイアの集中力、恐るべし!!もはや、プロの仕事!

新型コロナ禍、ようやくマスクが取れた!
それにしても、すごい思い出ですよね!ジュニアクワイアの近くで歌っていたプロの歌手は、だいぶ世界的な人たちですよ!
こんな経験、滅多にできるものではありません!
世界中の合唱団は、新型コロナ禍で非常に厳しい状況に置かれました。ジュニアクワイアも例外ではありません。ようやくノーマスクでの演奏が可能となってきましたが、高校3年生はまもなく引退となります。
今回出演したメンバーの一人、福澤心さん(18)は「ようやくマスクを外して歌えるようになった。最後の年になったけれど、間に合ってうれしい」と笑顔でした。
「もう一度舞台に立てたなら」
同じく高校3年生の水元葉奈子さん(17)は「小学5年の時に(別公演の)ボエームに出演したことがある。今回は練習時間が少なく間に合うか心配だった。でも、本番ではいつも通りの力を出すことができた」と明かしてくれました。鈴木理帆さん(17)は「当日まで頑張って歌詞を覚えた。本番では間違えずに歌えてよかった」と、語ってくれました。
3人とも、もう一度あの舞台に立ちたい!と口を揃えていました。
今回の「ボエーム」は、二重三重に特別な公演だったのですね!
当日は、出演者用の館内アナウンスも全てイタリア語だったそうです(そりゃあそうか…)。海を渡ってきた大きな舞台装置を間近にして、子供たちもテンション上がりますよね…!
私の愛聴盤をご紹介します
① ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ベルリンフィル 1972年ミレッラ・フレーニ(ミミ)、ルチアーノ・パヴァロッティ(ロドルフォ)など

(ポリドール 1990年)
②トゥリオ・セラフィン指揮 ローマ・聖チェチーリア音楽院管弦楽団 1959年
レナータ・テバルディ(ミミ)、カルロ・ベルゴンツィ(ロドルフォ)など

(ポリドール 1985年)
③アントニーノ・ヴォットー指揮 ミラノ・スカラ座管弦楽団 1956年
マリア・カラス(ミミ)、ジュゼッペ・ディ・ステファノ(ロドルフォ)など

(EMI 1987年)
どれも中古で入手可能です。
雄弁かつ圧倒的な表現力は①、
イタリアの劇場の雰囲気と様式感は②、
カラスの歌唱は譲れないという向きには③がオススメ。
▼ちょっと補足情報
新型コロナが落ち着きを見せ、ジュニアクワイアでも、新入団員を積極的に募集しているそうです。ご興味あればWebサイトを覗いてみてください。
https://www.hcf.or.jp/bunka/jojc/
では、また。
※舞台と出演者の写真は浜松市文化振興財団提供。



 シェア
シェア ポスト
ポスト LINEで送る
LINEで送る