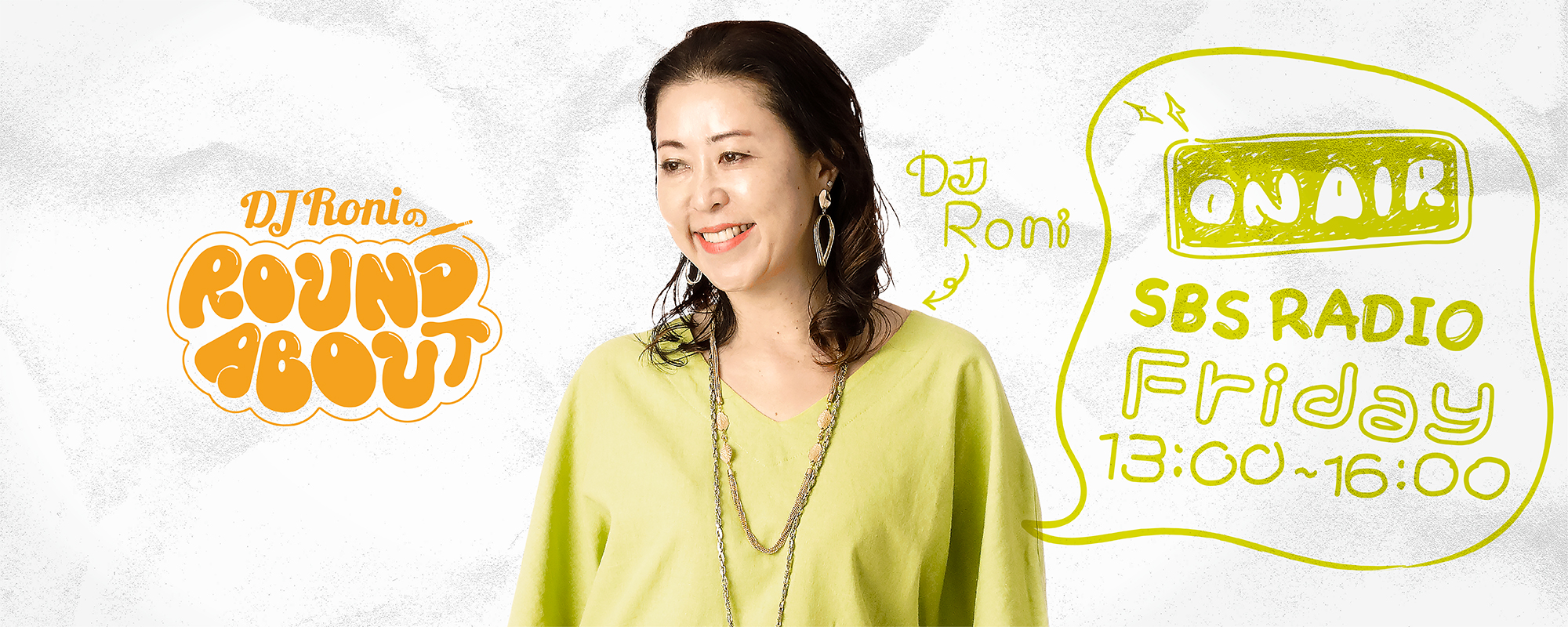2025.07.04
DJ Roniの 海 Roniプロジェクト 鈴与Presents 清水港ポートアバウト
毎月第4週は「鈴与Presents 清水港ポートアバウト」のコーナー、清水の海に深くかかわる、鈴与株式会社の協力のもと、清水港に関連する仕事や、そこで働く人、清水港の環境問題などにスポットを当てていきます。
今回の海Roniプロフェッサーは、静岡市清水区にある「フェルケール博物館」の副館長で学芸部長 の椿原靖弘さん。テーマは「清水の缶詰の歴史」です。
静岡市清水区(旧清水市)は、まぐろ類缶詰(ツナ缶)の生産量は全国1位!「フェルケール博物館」には、清水の缶詰に関する貴重な資料もたくさん保存されています。
1928年に現在の静岡県水産・海洋技術研究所で製造予備試験を開始すると、その1年後にはアメリカへ輸出。ニューヨーク市場で市販され、大変な好評を得たことから、1930年に清水食品株式会社、1931年には、後藤罐詰所(後のはごろもフーズ)が創業し、アメリカへの輸出を開始しました。静岡は全国屈指のマグロ・カツオ漁港である焼津港、清水港がある一方で、日本一のミカン産地でした。昭和初期には現在のようにマグロを冷凍しておけなかったため、マグロだけで 1年中缶詰を作ることは難しかったのですが、静岡では冬にとれるミカンがあったため、夏はマグロ、冬はミカンというように缶詰を一年中作ることが可能で、工場を休ませる必要がなかったそうです。
最近の清水の缶詰産業は、ツナ缶以外にも、ご当地缶詰として「富士宮やきそば缶」、「清水もつカレー缶」、「静岡おでん缶」なども人気です。


 △清水で最初に作られたツナ缶のラベルと、1975年から海外への支援物資として送られているツナ缶の統一パッケージ。
△清水で最初に作られたツナ缶のラベルと、1975年から海外への支援物資として送られているツナ缶の統一パッケージ。
コーナーの感想や、皆さんが撮影した海の写真などは、是非「#海Roni」を付けてSNSにアップしてくださいね。